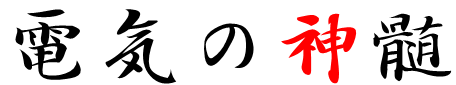本記事では、第二種電気工事士筆記試験のうち「令和元年度上期 問21~30」について解説する。
問21
店舗付き住宅の屋内に三相3線式200V,定格消費電力2.5kWのルームエアコンを施設した。
このルームエアコンに電気を供給する電路の工事方法として、適切なものは。
ただし、配線は接触防護措置を施し、ルームエアコン外箱等の人が触れるおそれがある部分は絶縁性のある材料で堅ろうに作られているものとする。
イ.専用の過電流遮断器を施設し、合成樹脂管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
ロ.専用の漏電遮断器(過負荷保護付)を施設し、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
ハ.専用の配線用遮断器を施設し、金属管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
ニ.専用の開閉器のみを施設し、金属管工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
解説
住宅の屋内電路の対地電圧は、$150\mathrm{V}$以下としなくてはならないため、それ以外の場合は下記の措置を施す必要がある。
- 簡易接触防護措置を施す。
- 電気機器は屋内配線と直接接続する(コンセントは使用不可)。
- 専用の開閉器および過電流遮断器を施設する。
- 漏電遮断器を施設する。
であるから、「ロ」は適切となる。
関連記事
類題
問22
床に固定した定格電圧$200\mathrm{V}$,定格出力$2.2\mathrm{kW}$の三相誘導電動機の鉄台に接地工事をする場合、接地線(軟銅線)の太さと接地抵抗値の組合せで、不適切なものは。
ただし、漏電遮断器を設置しないものとする。
イ.直径$1.6\mathrm{mm},10\Omega$
ロ.直径$2.0\mathrm{mm},50\Omega$
ハ.公称断面積$0.75\mathrm{mm^2},5\Omega$
ニ.直径$2.6\mathrm{mm},75\Omega$
解説
問題の機器は$300\mathrm{V}$以下に該当するため、D種接地工事を施工する。
接地抵抗値は$100\Omega$以下、接地線(軟銅線)の太さは直径$1.6\mathrm{mm}$以上である(漏電遮断器の設置がない場合)。
選択肢のうち、ハの公称断面積$0.75\mathrm{mm^2}$は、直径に換算すると約$1\mathrm{mm}$となるので不適切である。
よって「ハ」が正解となる。
関連記事
類題
問23
図に示す雨線外に施設する金属管工事の末端Ⓐ又はⒷ部分に使用するものとして、不適切なものは。
イ.Ⓐ部分にエントランスキャップを使用した。
ロ.Ⓑ部分にターミナルキャップを使用した。
ハ.Ⓑ部分にエントランスキャップを使用した。
ニ.Ⓐ部分にターミナルキャップを使用した。

解説
エントランスキャップとターミナルキャップの使用に関しての問題である。
エントランスキャップは少し斜めを向いた形をしており、ターミナルキャップは真下を向いた形をしている。
問題の図のⒶにはエントランスキャップは使用できるが、ターミナルキャップは使用できない。
なお、図のⒷにはエントランスキャップおよびターミナルキャップの両方が使用できる。
上記の条件より「ニ」が不適切な選択肢となる。
関連記事
類題
問24
図のような単相3線式回路で、開閉器を閉じて機器Aの両端の電圧を測定したところ$150\mathrm{V}$を示した。
この原因として、考えられるものは。

イ.機器$\mathrm{A}$の内部で断線している。
ロ.$\mathrm{a}$線が断線している。
ハ.$\mathrm{b}$線が断線している。
ニ.中性線が断線している。
解説
電圧計による測定に関する問題である。
$\mathrm{a-b}$線間が$200\mathrm{V}$であることから、中性線に不具合がなければ、機器$\mathrm{A}$が$150\mathrm{V}$になることはないと判断できる。
- 機器$\mathrm{A}$の内部で断線している場合は、電流が流れなくなり$0\mathrm{V}$になるから、イは不適切である。
- $\mathrm{a}$線が断線した場合は、機器$\mathrm{A}$に電流が流れなくなり$0\mathrm{V}$になるから、ロは不適切である。
- $\mathrm{b}$線が断線した場合は、機器$\mathrm{B}$に電流が流れなくなり、機器$\mathrm{A}$に電圧$200\mathrm{V}$がかかるため、ハは不適切である。
よって「ニ」が正解となる。
関連記事
類題
問25
使用電圧が低圧の電路において、絶縁抵抗測定が困難であったため、使用電圧が加わった状態で漏えい電流により絶縁性能を確認した。
「電気設備の技術基準の解釈」に定める、絶縁性能を有していると判断できる漏えい電流の最大値$[\mathrm{mA}]$は。
イ.$0.1$ ロ.$0.2$ ハ.$1$ ニ.$2$
解説
低圧電路の漏えい電流は、$1.0\mathrm{mA}$以下にすることが必要である。
よって「ハ」が正解となる。
関連記事
類題
問26
工場の$200\mathrm{V}$三相誘導電動機(対地電圧$200\mathrm{V}$)への配線の絶縁抵抗値$[\mathrm{M\Omega}]$及びこの電動機の鉄台の接地抵抗値$[\Omega]$を測定した。
電気設備技術基準等に適合する測定値の組合せとして、適切なものは。
ただし、$200\mathrm{V}$電路に施設された漏電遮断器の動作時間は$0.1$秒とする。
イ.$0.2\mathrm{M\Omega} 300\Omega$
ロ.$0.4\mathrm{M\Omega} 600\Omega$
ハ.$0.1\mathrm{M\Omega} 200\Omega$
ニ.$0.1\mathrm{M\Omega} 50\Omega$
解説
絶縁抵抗値及び接地抵抗値に関する問題である。
絶縁抵抗値は「$0.2\mathrm{M\Omega}$以上」または接地抵抗値は「$500\Omega$以下」となる。
上記の値に適合する「イ」が正解となる。
関連記事
類題
問27
単相3線式回路の漏れ電流の有無を、クランプ形漏れ電流計を用いて測定する場合の測定方法として、正しいものは。
ただし、選択肢の図の網掛け線は中性線を示す。

解説
クランプ形漏れ電流計に関する問題である。
漏れ電流の有無を調べるには、3本すべてをクランプする必要がある。
よって「ニ」が正解となる。
類題
問28
電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。
イ.電気工事士は、都道府県知事から電気工事の業務に関して報告するよう求められた場合には、報告しなければならない。
ロ.電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯しなければならない。
ハ.電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するよう作業を行わなければならない。
ニ.電気工事士は、住所を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
解説
電気工事士の義務または制限についての記述のうち、住所の変更をしたときは、免状に自分で訂正する。
(住所変更をした場合には書換えする必要はなく、自身で免状裏面の住所欄に新住所を記入する)
よって「ニ」の記述が不適切である。
関連記事
類題
問29
電気用品安全法における電気用品に関する記述として、誤っているものは。
イ.電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品安全法に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
ロ.特定電気用品には下記のマーク

または(PS)Eの表示が付されている。
ハ.電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない電気用品を販売してはならない。
ニ.電気工事士は、電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
解説
電気用品安全法の問題である。
ロは「特定電気用品以外の電気用品の表示」の説明となる。
特定電気用品には、下記のマーク

または表示面積が小さい場合などは、<PS>Eの記号を表示する。
よって「ロ」が正解となる。
関連記事
類題
問30
一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。
イ.低圧で受電するもので、出力$60\mathrm{kW}$の太陽電池発電設備を同一構内に施設するものは、一般用電気工作物となる。
ロ.低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
ハ.低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
ニ.高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、一般用電気工作物とならない。
解説
一般用電気工作物の適用を受けるものは、低圧受電するものである。
- 「太陽電池発電設備」は出力が$50\mathrm{kW}$未満であれば、一般用電気工作物となるため、イの記述は不適切である。
- 低圧受電で小出力発電設備であるから、一般用電気工作物であり、ロは適切である。
- 火薬類を製造する事業場に設置するものは一般用電気工作物ではないため、ハは適切である。
- 高圧受電であるから、一般用電気工作物ではないため、ニは適切である。
よって「イ」が正解となる。
関連記事
類題
この年度の他の問題
技能試験 2023年度候補問題 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.1 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.2 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題N[…]
著書・製品のご紹介
『書籍×動画』が織り成す、未だかつてない最高の学習体験があなたを待っている!
※本ページはプロモーションが含まれています。―『書籍×動画』が織り成す、未だかつてない最高の学習体験があなたを待っている― 当サイト「電気の神髄」をいつもご利用ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。[…]
この講座との出会いは、数学が苦手なあなたを救う!
電験アカデミアにテキストを書き下ろしてもらい、電験どうでしょうの川尻将先生により動画解説を行ない、電験3種受験予定者が電…
すべての電験二種受験生の方に向けて「最強の対策教材」作りました!
※本ページはプロモーションが含まれています。すべての電験二種受験生の方に向けて「最強の対策教材」作りました! 当サイト「電気の神髄」をいつもご愛読ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。 […]
初学者が躓きがちなギモンを、電験アカデミアがスッキリ解決します!
※本ページはプロモーションが含まれています。 当サイト「電気の神髄」をいつもご利用ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。 2022年5月18日、オーム社より「電験カフェへようこそ[…]