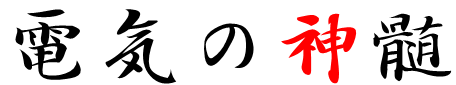本記事では、2023年度第二種電気工事士技能試験において、電気技術者試験センターから公表されている候補問題のうち、No.6について取り上げる。
解説動画
本動画では、複線図を書く手順と作業の流れを解説している。
本記事では電気工事士の技能試験で行う単一作業を動画で解説している。試験勉強に活用してほしい。VVFストリッパーの使用方法VVFストリッパーは第二種電気工事士および第一種電気工事士の技能試験を突破する上でとても重要な工具である[…]
単線図
図1に本問の単線図を示す。この単線図は電気技術者試験センターから公表されている。
記載寸法は過去の問題を元に独自に予想したものであり、試験当日は問題をよく読んでから作業を開始してほしい。

図1 単線図
施工条件
下記に本問の施工条件を示す。
- 配線および器具の配置は、図1に従って行う。
- 3路スイッチの記号「0」の端子には電源側または負荷側の電線を結線する。
- 3路スイッチの記号「1」と「3」の端子にはスイッチ相互間の電線を結線する。
- 電源からの接地側電線には、すべて白線を使用する。
- 電源から3路スイッチSおよび露出形コンセントまでの非接地側電線には、すべて黒線を使用する。
- 引掛シーリングローゼットの接地側極端子(Wまたは接地側の表示)には白線を結線する。
- 露出形コンセントの接地側極端子(Wの表示)には白線を結線する。
- VVF用ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けること。
- A部分の接続箇所は、差込形コネクタによる接続とする。
- B部分の接続箇所は、リングスリーブによる終端接続とする。
- 露出形コンセントの結線は、ケーブルを挿入した部分に近い端子に結線すること。
この施工条件は候補問題および過去の問題から予想して作成したものであり、実際の問題と表現の方法が少し異なるが、大きく変わることはない。
試験当日は、接続方法などが変わることがあるため、施工条件をよく読んでから作業を開始してほしい。
使用材料
表1に本問の使用材料を示す。
表1 使用材料
| 材料名 | 寸法[mm] | 数量 |
|---|---|---|
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)青色 平形2.0mm 2心 | 250 | 1本 |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 平形1.6mm 2心 | 850 | 1本 |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 平形1.6mm 3心 | 1050 | 1本 |
| 引掛シーリングローゼット(角形) | 1個 | |
| 露出形コンセント | 1個 | |
| タンブラスイッチ(3路) | 2個 | |
| 埋込連用取付枠 | 2枚 | |
| リングスリーブ(小サイズ) | 4個 | |
| 差込形コネクタ(2本用) | 2個 | |
| 差込形コネクタ(3本用) | 2個 |
表1の使用材料は、候補問題および過去の問題から予想して作成したものである。
支給される器具やケーブルの寸法は大きく変わることはないが、接続方法によりリングスリーブや差込形コネクタの個数が変わる可能性がある。
試験当日は、問題に記載されている支給材料を良く確認してほしい。
複線図
図2に公表されている単線図を元に作成した複線図を示す。

図2 複線図
複線図を書かなくても作業は可能だが、接続間違いや刻印間違いを防止するために複線図を書くことをお勧めする。
練習を重ねれば、1~3分程度で書くことができる。定規やカラーペンを使って丁寧に書く必要はないので、電線の本数と色、刻印が分かるように書くこと。
動画では、音声付きで書く手順を解説しているので、参考にしてほしい。
その他の候補問題
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.1
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.2
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.3
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.4
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.5
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.7
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.8
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.9
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.10
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.11
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.12
- 2023年度第二種電気工事士技能試験 候補問題No.13
電気工事士向けコンテンツの一覧と、第二種電気工事試験について記載する。試験内容について第二種電気工事士の資格を取得するには、試験を受けて合格する方法と、所定の学校(経済産業大臣が指定した電気工事士養成施設)に通い定められた単位を取得[…]
著書・製品のご紹介
『書籍×動画』が織り成す、未だかつてない最高の学習体験があなたを待っている!
※本ページはプロモーションが含まれています。―『書籍×動画』が織り成す、未だかつてない最高の学習体験があなたを待っている― 当サイト「電気の神髄」をいつもご利用ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。[…]
この講座との出会いは、数学が苦手なあなたを救う!
電験アカデミアにテキストを書き下ろしてもらい、電験どうでしょうの川尻将先生により動画解説を行ない、電験3種受験予定者が電…
すべての電験二種受験生の方に向けて「最強の対策教材」作りました!
※本ページはプロモーションが含まれています。すべての電験二種受験生の方に向けて「最強の対策教材」作りました! 当サイト「電気の神髄」をいつもご愛読ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。 […]
初学者が躓きがちなギモンを、電験アカデミアがスッキリ解決します!
※本ページはプロモーションが含まれています。 当サイト「電気の神髄」をいつもご利用ありがとうございます。管理人の摺り足の加藤です。 2022年5月18日、オーム社より「電験カフェへようこそ[…]